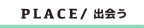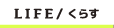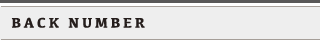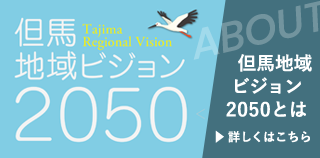国道9号から山陰の名湯・湯村温泉に入り、県道を南へ約2キロほど上った場所にある新温泉町丹土。急峻な峠道を抜けた先には、標高350メートルの、盆地状に広がる照来高原の美しい田園風景が迎えてくれます。
―のどかな田園風景
四方を愛宕山や草太山などの山々に囲まれ、すり鉢のような地形から照来盆地とも呼ばれています。照来盆地は、今から300万年前にできた照来カルデラの内側に堆積した泥や砂などでできた地質のため、地すべり地帯として知られ、地すべりによる緩斜面は棚田として利用されており、古くから稲作を中心に人々の営みが行われてきました。
盆地の中央に位置する丹土地区は、明治の町村制により7つの村が合併してできました。合併当時の中心だった地区で、照来村の役場が一時置かれたこともあります。
照来スキー場がかつてあったことから最盛期には民宿が10軒ほどあり、現在も但馬牧場公園やスキー場の入り口にあたり、観光業も盛んです。
名和牛・但馬牛のふる里としても有名で、田畑の耕作のために但馬牛は必要不可欠なものでした。昔はどの家にも玄関の横に牛の飼育スペースである厩があり、ひとつ屋根の下で人と牛が寝泊りしていた時代もあったそうです。
―清水が湧く丹土を歩く
村のシンボルとなっている「丹土清水」は集落の中央に位置しており、かつては生活用水として利用され、住民たちが集まる憩いの場でもありました。洗い場があり、洗い物や洗濯も行われていました。現在は主に防火用水として使用されています。
 (画像:<左>洗い物や洗濯が行われていた洗い場<右>丹土清水、湧水が流れ出ている様子)
(画像:<左>洗い物や洗濯が行われていた洗い場<右>丹土清水、湧水が流れ出ている様子)
清水には蛤の面白い話が伝わっています。ここには直径約5ミリの蛤に似た白い二枚貝がいました。しかし淡水に蛤はおかしいと、大正時代に京都大学の上治博士に鑑定を依頼したところ、マメシジミだと判明し、博士の名を取ってウエジマメシジミと命名されました。本来海にいるはずの蛤がいたことから、照来の七不思議として語り継がれています。
―氏神である熊野神社
ここからさらに山側に入っていくと、集落の氏神である熊野神社が佇んでいます。12月31日にはしめ飾りを神社に奉納する慣習が残っています。丹土では住民が10組に分けられ、毎日当番が旗を持ってお参りする日参が今でも行われています。昔は大きな旗を担いでお参りしていましたが、現在は小さな旗へと変わっています。境内には杉やイチョウなどの巨木が立ち並び、荘厳な社叢を創り出しています。平安時代に建立されたと伝わり、八幡神社も合祀されていることから、社殿には刀のオブジェも飾られています。
 (画像:<左>集落の氏神である熊野神社<右>奉納されたしめ飾り)
(画像:<左>集落の氏神である熊野神社<右>奉納されたしめ飾り)
神社のすぐ隣には「本覚寺薬師堂」があり、本尊は立派なもので、両脇の仁王像とともに古の雰囲気を今に伝えています。
神社から坂道を下って集落内に入ると、目に留まるのは梁の立派なしっかりした家々です。冬場は但馬でも雪の多い豪雪地域であり、頑丈さをもつ石州瓦の赤茶色の屋根と相まって、雪国特有の景観を醸し出しています。
お盆には、県無形民俗文化財である「丹土はねそ踊」が、公民館前で踊られます。「丹土はねそ踊」は戦国時代、豪族が我が家、我が身を守るため、家の子郎党に剣術を教えたことに由来します。2人、あるいは3人1組となって踊りを披露し、槍・懐刀・刀・なぎなたを手にして、太鼓とお囃子に合わせて演じます。剣術を元にして歌舞伎の音曲を取り入れた踊りは俊敏で、但馬でも珍しい民俗芸能です。毎夏の恒例行事であり、最後の踊りでは帰省客も飛び入り参加して、それぞれが自由に仮装して盛り上がるそうです。
丹土を見渡すなら草太山の中腹から眺めると、かつてカルデラ湖だった照来盆地の美しい田園風景と山々が一望できます。新緑の香る季節に、爽やかな高原の風に吹かれてのんびりと訪れてみたい場所でした。
LINK UP 照来の七不思議/丹土清水の蛤
| ■ 新温泉町観光ガイド [所]兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1 [HP]https://www.town.shinonsen.hyogo.jp/kanko.php |